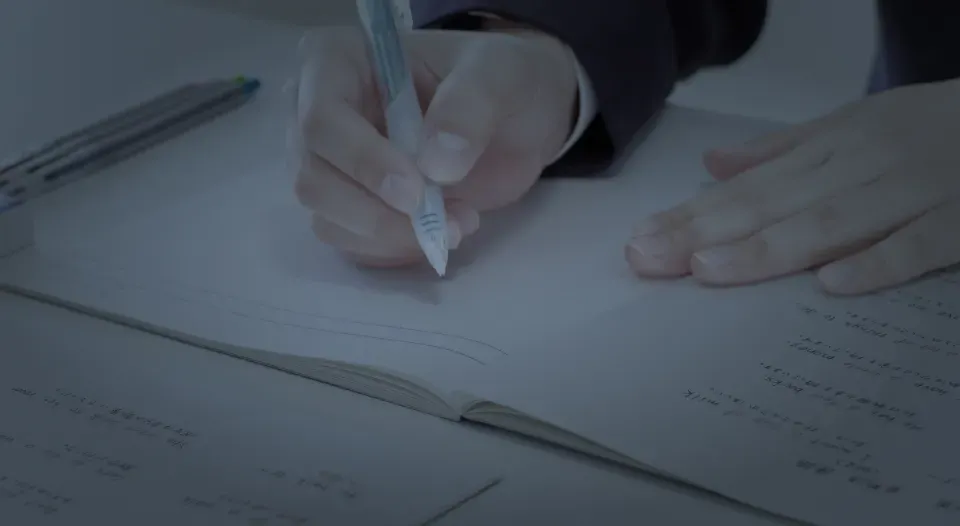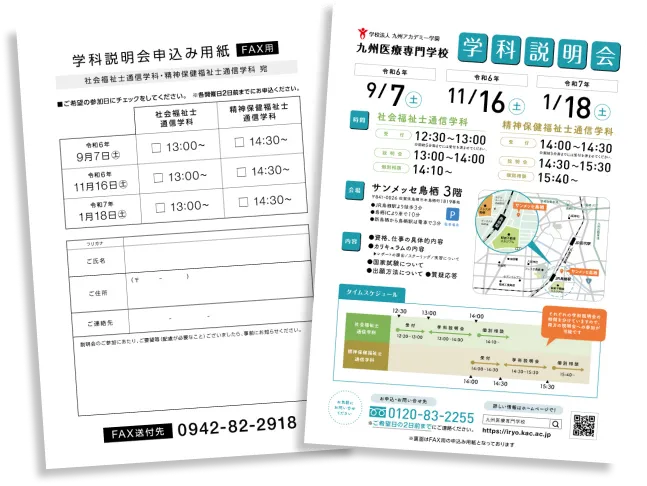この度、無事に合格することが出来ました。大変だったのは、仕事とレポート提出の両立でした。何とか全てのレポート提出を終え、本格的に試験勉強を始めたのは12月に入ってからでした。過去問題を中心に解き、わからない所や気になったところは教科書や参考書を読み返し、理解していきました。試験当日は、これまで積み重ねた勉強が自信となり、緊張することなく、落ち着いて解くことが出来ました。
この春から精神保健福祉士として働くにあたり、通信教育で学んだこと、これまで勉強してきた内容を忘れず、相手に寄り添える相談員になりたいと思っています。

30代女性
社会福祉協議会勤務

40代男性
高齢者施設勤務
まず大変だったのは、やはり勉強時間の確保でした。時には業務の関係で夜遅く帰宅することもありながら、試験勉強をする時間をつくる苦労の日々を思い出します。ある日は30分、ある日は2時間のように何とかして時間を割いては、過去問を解いたり教科書を開いたりしました。スクーリングでは、感染予防のために他の方々と接する機会を持つことが出来なかったものの、単に試験の勉強をするだけではなく、講師の方々の話を聞くことで思いもよらない発見がありました。これから受講される方々にとっても、スクーリングが多くの出会いの場になればと願っています。
社会福祉士を取得した際の受験勉強の方法が役に立ち、一回目の受験で精神保健福祉士を取得することが出来ました。仕事をしながらではありましたが、朝早く起きて勉強する時間を確保しました。なるべく毎日、勉強時間を確保するよう心掛けました。国家試験本番までに、180時間の勉強時間を確保しようと決め、勉強時間をアプリに入力して視覚化することで、勉強に対するモチベーションを保つことが出来ました。最後までモチベーションを保ちながら、諦めずに勉強を続けることで、試験当日には自分を信じて臨むことが出来ると思います。

20代男性
児童養護施設勤務

40代女性
高齢者施設勤務
本格的に受験勉強を開始したのは、10月頃からでした。11月~12月に実習があり、集中して取り組む時間の確保が思ったよりも取れなかったのが実際でした。そのため、隙間時間にアプリで問題を解いたり、家事をしながら動画配信サイトの動画を聞き流したりしながら、学習を進めていきました。勉強の時間をつくるのが難しい日は、別の日にその分の過去問題に取り組むなど、工夫をしながら過去問題にも取り組みました。諦めずに、繰り返し問題を解くことの大切さ、また、日々の積み重ねの大切さを実感しています。
社会福祉士を受験した際に、過去問を繰り返し解く勉強方法が最も有効だと感じたので、精神保健福祉士の国家試験に向けた勉強についても、過去問を解いていくこととした。あまり勉強に時間を割くのが好きではないので、なるべく集中して短時間でやっていこうと考え、11月から30分早く起きて、少しずつ問題を解いていくことにした。試験まで1か月を切ったところで、模擬問題集を購入し、図書館で時間を計りながら解いてみた。点数は微妙なラインで自信を無くすことにもなったが、試験の予行練習としてやって良かったと思う。

40代男性
障害者施設勤務
国家試験の勉強については、日常生活の中にある隙間時間を活用することをおすすめします。仕事、家事、育児を行う中で、講義動画や一問一答を聴きながら、一日に一つでも知識を増やすことを意識して、2年間を過ごしました。朝の通勤中に車の中で聴くことで、生活スタイルを変えることなく自然と頭に入りました。スクーリングの授業で学んだことやレポート課題をしっかり理解し、精神保健福祉士としての視点で考えることが出来れば、特別な勉強は必要ないと思いました。

30代男性
福祉施設勤務

60代女性
主婦
受講1年目はレポート提出するだけで精一杯でした。学習が進むにつれて、間に合うのだろうかという焦りもありました。しかし、還暦を過ぎており、年齢的にも1回で合格したいという思いがあり、「これまで頑張ってきたのだから合格する」と自分に言い聞かせて勉強を続けました。人物名や制度など暗記することが多いので、過去問や模擬問題を解くと同時に、動画サイトの講座を視聴することが有効でした。
通信課程は他の学生との交流も少なく、仕事をしながらの勉強は大変ですが、「絶対に合格する!」と自分を信じて頑張ってください。
入学してから卒業までの1年半は、レポート作成と実習に専念する期間でした。9月に卒業した後、国家試験の勉強に臨むこととなりましたが、やる気スイッチがなかなか入らず、試験勉強を開始したのは12月頃でした。どうにかギリギリの点数で合格することは出来ましたが、しっかりと計画を立てて学習を進めた方が良さそうです。

20代男性
福祉施設勤務

50代女性
福祉施設勤務
55歳で入学した私にとって、精神保健福祉士の合格通知は長年の夢がかなった喜びと感謝、そしてこれからの人生の指針となりました。私には、「1回で合格したい」という強い気持ちがありました。そのため、早い段階で過去問を解きはじめ、覚えるべきことをノートにまとめていきました。また、携帯のアプリを購入し、ゲーム感覚で楽しく取り組むことも出来ました。スクーリングで出会った若い仲間からは、国家試験対策にと動画サイトの講義を進められました。この動画を家事や移動の合間に聞き流し、これも合格の大きな助けとなりました。
スクーリングの科目毎に行われる復習テストで、毎回30%程度しか点数が取れていませんでした。この時点で、学校から推薦される学習教材や模試等は全て取り組むことにしました。いろいろと参考になる情報は学校から提供されますので、惜しみなく活用しました。また、自分でもWebサイトなどを見つけ、見つけたサイトを学ぶツールとして活用しました。時間をはかりながら問題を解き、自己採点を正確に行うこととしました。選択肢のこの部分がこうなったら正しい文章になる、という点に着目し、ノートにまとめてみることをお勧めします。

50代男性
教育機関勤務

40代男性
福祉施設勤務
国家試験の勉強を本格的に開始したのは11月頃だったと思います。平日は1時間程度、休日は3~6時間程度の学習でした。時には学習できない日もありました。可能であれば、少しでも早く学習をスタートすることを進言します。勉強に活用したものとしては、Webサイト、過去問題集及び参考書、動画配信サイトです。特に重要なことは、試験前の体調管理です。私は、試験の1週間前から有給をもらい、試験の数日前から試験会場近くのホテルで体調を整えて臨みました。最後まであきらめなければ、1%でも合格の確率は上がると思います。